第一章 秋の章「温泉地の秋」
6.街を歩く(その2)
そうだ、小学校低学年のころ、学校で母の日の前に作ったっけ。『お手伝い券』『肩たたき券』『おつかい券』これを何枚かまとめて母の日に、カーネーショ
ンと一緒に送ったような気がする。母も、そのころを思い出して、優しい目になっている。
「あのころ、翼、可愛かったのよ。ママが熱を出すと、せっせとタオル冷やしてくれたり…。お手伝い券で家中、掃除してくれたことあったわよね」
遠くを見るような目で話してくれる。昔は、ママだってもっと若くて、元気で、楽しそうだったよな。いつからこんなに遠い関係になっちゃったんだ
ろう。ふと気づくと、元気な女性の一群が通り過ぎた。花のようなメンバーの中に、地味だがひときわ清楚な印象のひとがいた。
「あ、遼子さん!」
翼は手を振った。祖父母も挨拶をする。どうやらこれは、温泉療養セラピストのみなさんらしい。みな、ノーメークだが、肌はとびきりきれいだ。お
しゃれのしがいがあるというものだろう。彼女は翼たちに気づき、明るく手を振った。
「後から連絡入れます!」
翼がぼやっとしながら突っ立っていたので、母が脇の下をこづいた。
「だ~れ、あれ。なんだか、きれいなお嬢さんねえ」
その声には揶揄する響きはなかった。
「ここの温泉セラピストさんだよ。おじいちゃんたちが世話になっているんだ」
「ふうん、ここにいると、あんなにきれいになれるのかしらね」
「元ネタによるんじゃない?」
「悪かったわね!」
こんなふうに、母と軽口をたたくなんて、ひさしぶりかも。家庭内の電子掲示板にケータイメール、電話など、デジタルを介しての会話が中心で、じ
かに会って話しすること、今ではすごく少ないもんな。
祖母のルイカが、青く光った。
「おや、こんな朝早くから、チョボラのお願いだわ。何かしら?」
「ちょぼら?何それ?」
祖母はルイカを操作している。すごく手馴れている!
「ちょっとボランティアってやつだよ。これも、感謝券が使われる」
祖父が耳打ちしてくれた。
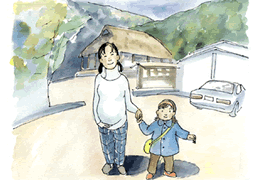
「あらあら、大変、三丁目の岸上さんの奥さん、具合が悪くて幼稚園のお見送りにいけないんだって。早速OKの返事しようっと」
祖母はすたすたと歩き出した。三丁目の岸上さんのご自宅までルイカに道案内が出ているらしい。結構、坂も階段もある。岸上さんの家まで来てルイ
カのボタンを押した。三十代始めと思われる奥さんがゆっくり出てきた。おなかが真ん丸い。
「臨月だ!」
翼は眼を丸くした。
